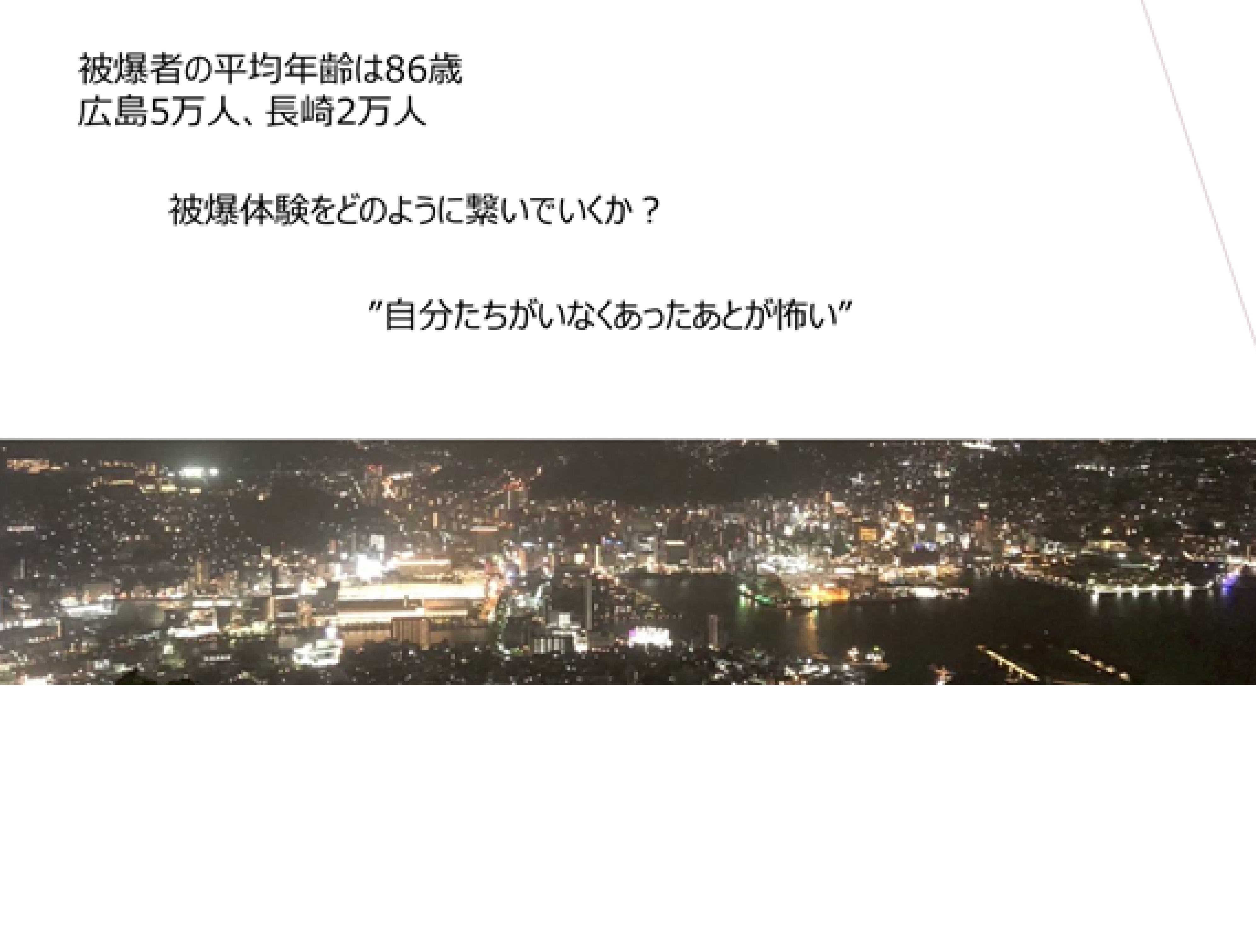原水爆禁止世界大会2025(長崎)の参加報告会を開催しました。(パート1)
9月8日、原水爆禁止世界大会(長崎)に参加した3名の報告会を開催しました。今年は戦後80年・被ばく80年の年となります。参加した職員から豊かな経験を得られたことが報告されました。参加した職員の報告を3回に分けて掲載します。
1日目は結団式で参加者の抱負を発表し合った後、原爆被害者の支援を行っている方のお話を聞きました。原爆小頭症で社会になじめず、思うように働けない環境下で最期まで楽しいことは何もなかったと話された方のエピソードが印象に残りました。原爆投下当時は生まれてもいなかったのに、生涯にわたって原爆の影響を受け続けたと知り、原爆が与える影響の大きさを改めて学びました。
2日目はそれぞれが希望した分科会に参加しました。私は青年のひろばという若者向けの分科会に参加しました。そこでは原爆被害者の方のお話を聞いた後、その内容を踏まえて平和や原子力についてのグループディスカッションを行いました。お話してくださった方は「自分は家族を亡くしていないので他の人に比べれば恵まれている。語り部になる資格があるのかと自問した」と話されていましたが、小学生の時に親友を亡くし、焼け野原の中を荷物を抱えて40kmも移動したと語られており、当時の悲惨さは自分の想像を超えるレベルにあるのだなと感じました。グループディスカッションでは医療従事者、教育関係者、大学生が参加しており、それぞれの立場から平和や現在の問題について語り合いました。心と時間とお金に余裕がないとこのような平和活動に参加するチャンスが得られにくい、教育が差別や分断を生む思考のベースになってしまうことがあるなどの意見がありました。原爆被害者の方は、小さな差別や分断が戦争を呼んでしまう、と度々話されており、直近であれば新型コロナウイルス感染症が流行し始めた時も医療従事者への差別や偏見があったなと思い返しました。自分の中の偏見の種が大きな差別、分断につながる可能性が有るということを心に留めておきたいです。
3日目のナガサキデー集会では世界各国の方々が集まり、「核抑止ではなく核廃絶を」という考えのもとにスピーチを行っていました。ウクライナやパレスチナ、ガザなどの現在起きている争いについても言及されていました。原爆被害者の方々は、自分たちがいなくなった後が心配であると話されていました。「今日の聞き手は明日の語り手」の言葉通り、現地で生の声を聞き、直接質問までできるという貴重な経験をした自分が筆頭に、原爆被害を語り継ぎ、矮小化させないようにせねばと強く思います。
東区ひまわり薬局 薬剤師 (H.H)